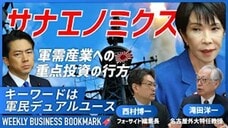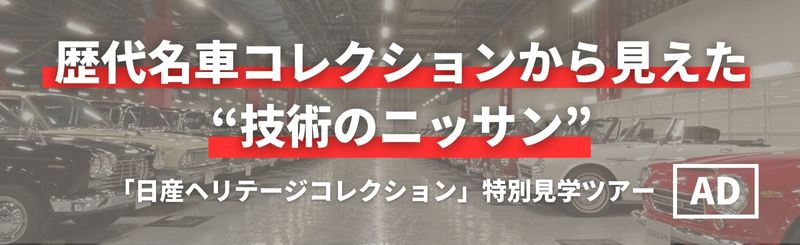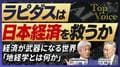世界経済の牽引車の歴史的交代がおよそ30年ぶりに進みつつある。1990年代半ば以降、グローバル企業の生産拠点を引き寄せ、輸出、雇用を拡大、高成長を続けてきた中国が失速、代わってインドが幅広い産業分野で外資の直接投資を集め、「世界の工場」に名乗りをあげている。20世紀後半にアジアでは日本から韓国・香港・シンガポールなどアジアNIES(新興工業経済地域)へのシフト、ASEAN(東南アジア諸国連合)の台頭、中国の勃興という成長国・地域の連続的な交代が起きたが、2020年代に入って、インドが次の主役になろうとしている。
ただ、今回の交代劇は労働集約型産業に始まり、より高付加価値分野に段階的に進む従来の産業シフトと異なり、半導体、電子デバイス、スマホなど先端産業の移転も一斉に進む“産業雪崩”の様相を示している。米中対立による産業分断、インドの豊富な理工系人材がグローバル企業の劇的なインド傾斜を引き起こす要因となっている。
中国と抜きつ抜かれつの500年
インドは8月23日の月探査機「チャンドラヤーン3号」の月面着陸成功に続き、9月2日には太陽観測衛星「アディティヤL1」の打ち上げに成功した。月面着陸は米、ロシア、中国に次ぐ4カ国目で、日本に先行した。
政府、企業、大学などの科学技術分野における研究開発支出(2020年、UNESCO=国連教育科学文化機関統計)では、インドは米国の約12分の1、中国の約10分の1に過ぎない。にもかかわらず、インドが宇宙開発で存在感を示すのは研究開発の人的資源の厚みがあるからだ。サイエンス系学位(理学、工学、医学と行動科学など一部の社会科学の学士、修士、博士の合計)の年間取得者数(NSF=アメリカ国立科学財団集計、2018年)は、インドがトップの229万人で、2位の中国の182万人、3位の米国の81万人を大きく引き離している。日本は第9位で17万人にすぎない。高等教育の在籍学生数(2021年、UNESCO統計)では中国が5382万人とインドの3887万人の1.4倍の規模だが、自然科学専攻の比率がインドの19.5%に対し、中国は8.4%に止まっているためだ。
一方で、IMF(国際通貨基金)統計では2022年のインドの名目国内総生産(GDP)は世界第5位の3兆3864億ドルで、米国はその7.5倍、中国は5.3倍のGDP規模を持つ。物価水準の差を考慮した購買力平価GDP(IMF統計、2022年)でみても、インドに対し中国は2.5倍、米国は2.2倍の規模。インドが中国に代わる世界経済の牽引車になるには、依然として力不足は否めない。
だが、中国とインドとの経済規模の推移を歴史的にみれば、両国がシーソーゲームのように抜きつ抜かれつしてきたことがわかる。世界各国・地域の長期間のGDP推定で知られる英国の経済学者、アンガス・マディソン氏によれば(すべて1990年の価値に換算)では、1500年に中国のGDPは618億ドル、インドは605億ドルと拮抗していた。その後、インドはイスラム教のムガル帝国となり、17世紀のシャー・ジャハンと息子、アウラングゼーブの治政期に最大の版図を築くなど繁栄し、1700年にはインドのGDPが907億ドル、中国が828億ドルとインドが逆転した。だが、18世紀の中国は……
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。