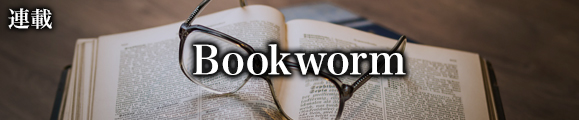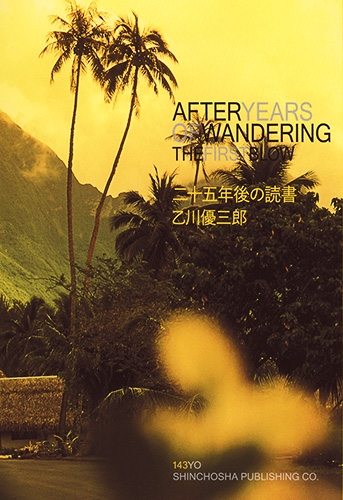時代小説の名手が描いた
「作家と書評家」の物語
「因果なことに二人は文学に生かされていた」と作者が語る男女の物語である。そして、ある意味、無いものねだりの作品でもある。
男は、円熟期にさしかかった作家、三枝昂星(さえぐさこうせい)、本名谷郷敬(やごうたかし)。そして女は、旅行業界紙の記者からエッセイストを経て書評家へと転じた中川響子(きょうこ)。2人は、30年前、パラオで結ばれた男と女の関係でもある。
さて、近年、すっかり時代小説から現代小説、あるいは近未来小説へとシフトした乙川優三郎だが、冒頭、響子が親類の葬儀へ行く場面では、あの時代小説に共通する巧緻繊細な筆致は活きている。
話が作家と書評家の物語故、私は当初、後者に思い入れをして読んでいくことになるのだろうと思ったのだが、どうも、雲行きが怪しくなって来た。それは、自分が30年以上身を置いている書評の世界におけるリアリティーが、どのくらいこの作品で反映されているか、という問題とも深く関わっているからだ。
担当編集者の勧めで、1本の書評を書いた響子は、その良質な酷評故、あたかも次世代の書評界を牽引していく存在の如く評価され、彼女のところへはたちどころに献本の山が築かれる。が、これは下手をすれば、その良質な酷評の方がクローズアップされる場合があり得るので、これは諸刃の剣である。
確かに作家を育てるための酷評は必要だが、まず響子が最初に頼まれた書評の枚数が8枚から10枚だが、これは文庫の解説の長さであり、いま新聞等で最もスタンダードな書評枚数は2枚である。その中で作家を育てる良質な酷評を入れることはむずかしい。
私の場合、時代小説が専門だが、ジャンルの隆盛に寄与する作品の良質な点を評価するのが精一杯で、酷評が必要な作品はハナから黙殺する。
一方、リアルな点でいえば、響子が書評でも美しい日本語を追求する余り、自律神経を病む箇所で、私もその伝でうつ病になった経験がある。
そして彼女が療養に訪れた南方の島で完璧に美しい小説=ストーナーの作品に思いをはせ、マン兄弟を研究しているという老人が「人間に良心があるうちは文学は廃(すた)れない」と語りかけてくる場面は美しい癒しのそれといえよう。文体でいえば、文学論的箇所は息詰まる迫力、それに反して、カクテルを語るくだりは、私が下戸なためか、やや浮薄な気がした。
12月に姉妹篇、『この地上において私たちを満足させるもの』が刊行されるので、こちらも楽しみだ。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。