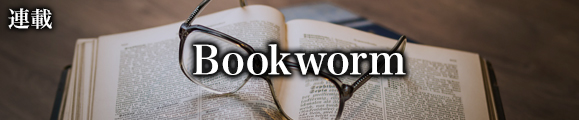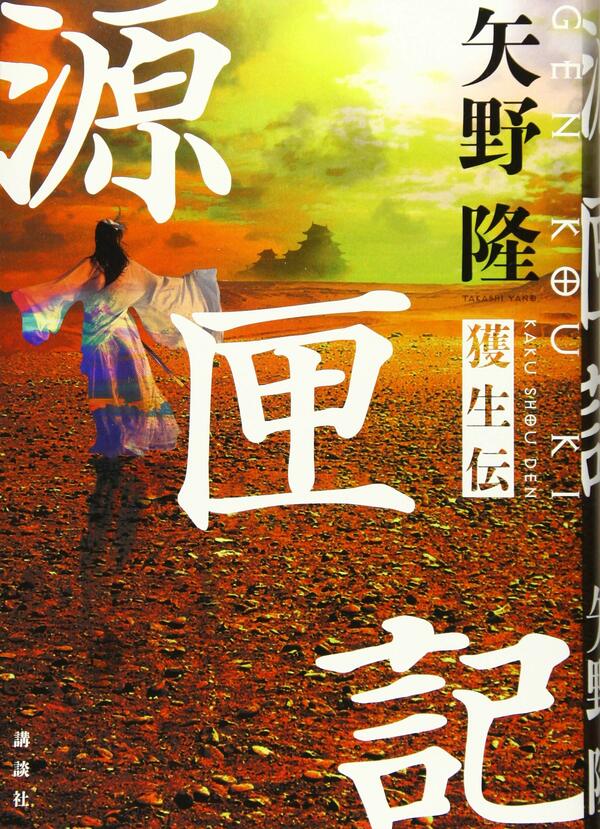400ページ超も怒涛の一気読み‼
ヒット必至の超弩級歴史ファンタジー
つい先日も、明治期に入ってからの新撰組の残党の生きざまを活写した傑作『至誠の残滓』を刊行した矢野隆が、超弩級の書き下ろし歴史ファンタジーをものした。それも400ページを超える大部の巨篇で、これが幕明けの1巻となるという。
帯の惹句にあるように、舞台となるのは日華融合の架空の大陸で、その中で、さまざまな史観やイマジネイションが炸裂する。私見ではこの大作は『指輪物語』や『十二国記』等に匹敵する可能性を孕んでいる、と思われる。
ことの発端は、ある日、突然、大陸に現われた巨大な山・真天山の頂上に存在する巨大な「源匣(げんこう)」から、膨大な力を分け与えられた無数の「小匣(こばこ)」が放たれたことに依る。「小匣」は人と人とを繋ぐことができ、これを抱いた真族たちは大陸の覇者となり、王朝を築いた。「小匣」には、己の運命を暗示する「天字」と呼ばれる一文字が刻まれており、稀に「源匣」の持つ力を一時的に引き出す「奉天」という現象を引き起こすことができる。こうして真族が大陸を支配し、被征服民の「緋眼」は、その圧政に苦しんでいた。
主人公である木曾捨丸は、村長である父の謀反の企てが発覚、目の前で両親を殺され、怒りにまかせて真族の1人から「小匣」を奪い、獲生(かくしょう)と名を変えて、さすらいの旅に出る。奪った「小匣」に記されている文字は、“棄”であった。
このくだりでの捨丸の思い――「緋眼であることを、この村を、全てを棄てる」は実に切ない。
が、物語は読者にそんな余韻を感じる暇も与えずパワフルに突き進んでゆく。そしてさまざまな人物との出会い――たった1人だけ「小匣」を開けたことのある男・宝超、盤海・娘鈴(こりん)父娘が率いる旅一座の芸人たち(この旅の芸人が法の埒外におり、自力救済を口にするくだりは、隆慶一郎が網野善彦の中世史学から引用した「道々の輩」「公界の者」を思わせる)。獲生の兵隊仲間で、俺は帝になる男だ、とうそぶく転疾。さらに、武芸自慢のこの2人が束になってかかっても敵わない武來等々。
そして、獲生の旅は、父が死に際に遺した「風は何処より来たりて、何処へと吹きゆくのか」ということばの答えを求めてはじめられたものだが、あることから袂を分かった獲生と転疾のあいだにどのような運命が訪れるのか――これ以上は書けないが、400ページ怒涛の一気読みだ。長期シリーズとなる『源匣記』の今後に寄せる期待は大きい。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。