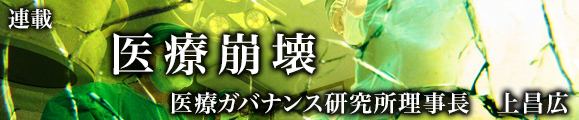小林製薬の紅麹問題をきっかけに健康食品の安全性についての議論が盛り上がっている。政府の規制を強化し、小林製薬の責任を問うべきだという声が強い。
紅麹を利用した多くの方々が、健康を害した。亡くなった方もいるという。心からお悔やみ申し上げたい。ただ、彼らの被害を強調し、規範論を盾に、このような主張をしても実効性は期待できるのだろうか。私は違和感を抱く。それは、世界の歴史から学んでいるように思えないからだ。
世界最古の健康食品「蜂蜜」にもリスクはある
健康食品の歴史は古い。世界最古の健康食品と言われているものの一つが蜂蜜だ。古代エジプト時代から食用および薬用として用いられた。蜂蜜は天然の甘味料で、抗菌作用や抗酸化作用もあるため、健康食品として重用されたらしい。エジプトのファラオの墓からも蜂蜜の壺が見つかっているという。
ただ、蜂蜜も使い方次第だ。過剰摂取は肥満や糖尿病を招き、齲歯(うし=虫歯)の原因にもなる。乳児に与えると、稀に乳児ボツリヌス症という食中毒を起こすことがある。蜂蜜中に混入している微量のボツリヌス菌が、免疫が不十分な乳児の腸管内で増殖し、便秘や哺乳力の低下などを来す疾患だ。このような合併症の存在が認知され、現在では、1歳未満の赤ちゃんには蜂蜜を控えるように推奨されている。
今回の紅麹問題も、本質的には蜂蜜の健康被害と変わらない。健康食品に限らず、人が作るものは汚染のリスクをゼロにできない。どの程度のリスクを許容するかだ。医薬品並みに規制せよという声もあるが、コスト面を考えれば現実的ではない。
私が注目する蜂蜜と紅麹の違いは、政府が何らかの形で安全性を保証しているか否かだ。政府の保証は、国民に安心を与え、企業には強力な支援となる。一方で、政府が中途半端な形で保証すれば、国民に被害が及ぶ可能性がある。
米国から20年遅れの日本
実は、このことは米国でとっくに社会問題化している。米国ボストン市在住の内科医である大西睦子医師は、「日本は米国を20年遅れで追いかけている」という。
彼女が注目するのは、アベノミクスの一環として2015年4月に導入された機能性表示食品制度が、1994年に米国で成立した「食品サプリメント健康および教育法(DSHEA法)」を雛形としていることだ。その基本的骨格は、そっくりと言っていい。
DSHEA法では、サプリメントを販売しようとする企業は、事前に米国食品医薬品局(FDA)の承認を必要としないことが法制化された。そして、企業は政府機関に届け出するだけで、ほぼ自由にサプリメントの安全性と有効性を記載することができるようになった。この結果、米国民は、サプリメントの安全性・有効性について、製造業者の主張を信じるしかなくなった。これ以降、米国でサプリメントによる健康被害が急増している。
このことは、様々な研究により実証されており、米国では臨床医学の重要な研究テーマとなっている。数多くの論文が発表されているが、最も有名な論文は、2015年10月に、FDAなどの研究チームが、権威ある米国の『ニューイングランド医学誌(The New England Journal of Medicine)』に発表したものだ。この研究によると、全米で、サプリメントの健康被害による救急外来受診数は、年間2万3000件で、2150件の入院が必要だったとされている。
この研究では、様々な合併症が報告されているが、最も多いのは、ダイエットや精力増強用のサプリメントで、動悸や不整脈などの症状が出ていたことだ。このようなケースの中には、本来は禁止されている成分などが混入している場合があることも、別の研究者によって報告されている。こうなると悪質だ。
『ニューイングランド医学誌』は、世界最高峰の臨床医学誌だ。この研究は、様々なメディアで報じられた。当然のことながら、米国でも、政府による規制強化の議論が盛り上がったが、急成長したサプリメント業界のロビー活動により規制は実現していない。例えば、2022年には、超党派の上院議員がサプリメント規制法案を連邦議会に提出したが、「サプリメント業界から献金を受けた議員が反対し、成立しなかった」(大西医師)という。このような事例は、州レベルでも存在する。DSHEA法成立後、急速に政治力をつけたサプリメント業界が、自らの利益を損ねかねない規制法に反対したという訳だ。
現在、日本政府は健康食品の規制を強化しようとしているが、おそらく同じ結果に終わるだろう。
安全性の担保に動いた米国の法曹・医学界
我が国での機能性表示食品の規制は、消費者庁が所管する食品表示法と、厚生労働省が所管する食品衛生法の二本立てだ。消費者庁は規制強化に前向きだが、食品衛生法の規制に関する議論は進んでいない。健康食品業界の多くは中小企業だ。大企業は兎も角、中小企業は安全情報の収集に対応できない。彼らの利益を代弁する族議員やその意向を受けた厚労省が、食品衛生法の改正に後ろ向きであることも頷ける。まさに、米国で起こったことと同じだ。
では、米国では、誰がサプリメントの安全性を担保しているのか。それは法曹界と医学界だ。前者については、言うまでもないだろう。大西医師は、「『サプリメントの健康被害がある人は、こちらにご連絡ください』のような法律事務所の宣伝が溢れています」という。
サプリメント訴訟の新規件数は、2019年65件、20年45件だ。和解に至った訴訟件数は公表されないので、これは氷山の一角だ。このような民事訴訟の多発が、サプリメント業界に強い圧力となっている。
医学界の貢献も大きい。米国の一流学術誌にはサプリメントの有効性や安全性に関する論文が溢れている。例えば、米国医師会が出版する『JAMA』は、タイトルに「Dietary Supplements」という単語を含む論文を16報掲載している。このうち13報は、1994年のDSHEA法制定以降に発表されたものだ。ちなみに、『ニューイングランド医学誌』も16報掲載している。
米国でサプリメントの健康被害の議論をリードするのは、ハーバード大学のピーター・コーエン准教授だ。『JAMA(Journal of American Medical Association)』に3報、『ニューイングランド医学誌』に8報の論文を発表している。
沈黙する日本医師会と東京大学
私が注目するのは、日本医師会や東京大学からは、健康食品の被害を訴える声が聞こえてこないことだ。この違いは興味深い。
私は、この差は日本と欧米の歴史にあると考えている。欧米において、医師は、弁護士、聖職者などとならび古典的プロフェッショナルと考えられている。報酬と引き換えに、自らのスキルを顧客のために使う。報酬は顧客からもらう。患者とは情報の非対称が存在するため、自己規律が重視される。このため、独自の職業規範が存在する。医師の場合、ヒポクラテスの誓いだ。
古典的プロフェッショナルは、ギリシャ・ローマ時代以来の歴史をもつ。その組織は幹部が対等な立場で経営に参画し、基本的に独立して活動するパートナー制だ。マッキンゼー・アンド・カンパニーの中興の祖と言われるマービン・バウアーが、コンサルタントを古典的プロフェッショナルとみなし、その職業規範や組織を構築したのは有名だ。
古典的プロフェッショナルが生きていくには、顧客の信頼を獲得しなければならない。サプリメントの健康被害に対して、医師が科学的に正確な情報を提供し、顧客との利益相反がないことを打ち出すのは、自らの利益に適っている。これが、サプリメント健康被害が社会問題化している米国で、多くの医師が論文を書き、『JAMA』などの一流誌が掲載する理由だ。
なぜ、日本でこうならないのか。それは日本の歴史に負うところが大きい。日本の医療界の雛形を作ったのは明治政府だ。近代化を急いだ明治政府は、東京帝国大学を作り、国家、つまり政府にとって有為な人材を育成した。法学部と医学部が中核を担ったのは、欧米の大学と同じだが、その教育の根底に古典的プロフェッショナリズムはなかった。
この「伝統」は、今でも引き継がれている。東大法学部の卒業生は、市民の個人の権利を守るのではなく、国家公務員になろうとするし、東大医学部の卒業生の多くは、患者を治療するよりも、医学研究で実績をあげ、大学教授となり、学会という業界団体で出世したいと希望する。
大学教員であれ、勤務医であれ、その身分は組織からの被雇用者、つまりサラリーマンだ。患者の信頼を失っても、収入が減ることはなく、組織内での評価も変わらない。給与は月給制だから、製薬企業や健康食品メーカーからの講演や監修を請け負っても、基本給を減らされることはなく、アルバイトをした分だけ収入は増える。この状況では、本業そっちのけでアルバイトに勤しむ医師が増えるのは当然だ。
健康食品問題は、国民の信頼を勝ち得るという点で、日本医師会にとってチャンスなのに、積極的に動く気配はない。日本医師会は『JMAジャーナル』という学術誌を発表しているが、健康食品問題には取り組んでこなかった。
余談だが、製薬企業が販促のために、講演料やコンサルタント料などの名目で医師に支払う製薬マネーも同様だ。医療ガバナンス研究所が取り組んできた日本における製薬マネー問題を、最も掲載してきた媒体は米国医師会誌(『JAMA』)や英国医師会誌(『BMJ(British Medical Journal)』)およびその姉妹誌だ。日本医師会の対応とは対照的だ。
「上医は国を医し…」を曲解した詭弁
日本の医療界の宿痾は、古典的プロフェッショナルが、国家に隷属し、組織の歯車になっていることだ。厚労省医系技官は、中国の六朝時代の陳延之の著書にある「上医は国を医し、中医は人を医し、下医は病を医す」を頻用する。病を医す医師と、国を医す政治家とは、本来、別の職業人だ。医系技官は、こんなことを言っておかしいと思わない。長いものに巻かれているうちに真っ当な判断力を失っている。
組織と古典的プロフェッショナルの相剋は、古今東西を問わず、繰り返し社会で議論されてきた。人体実験に従事したナチスの軍医たちが、ニュールンベルグ裁判で死刑判決を受け、処刑されたことなど、その典型だ。このような議論を積み重ね、世界では医師の職業規範が確立した。弁護士も同様だろう。これこそが、欧米社会でサプリメント被害から国民の健康を守る力になっている。
日本は、このあたりの議論が不十分だ。歴史的な幅広い視野から、職業人自らのあり方を考え直さねばならない。