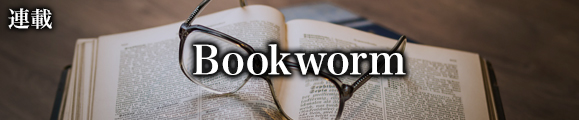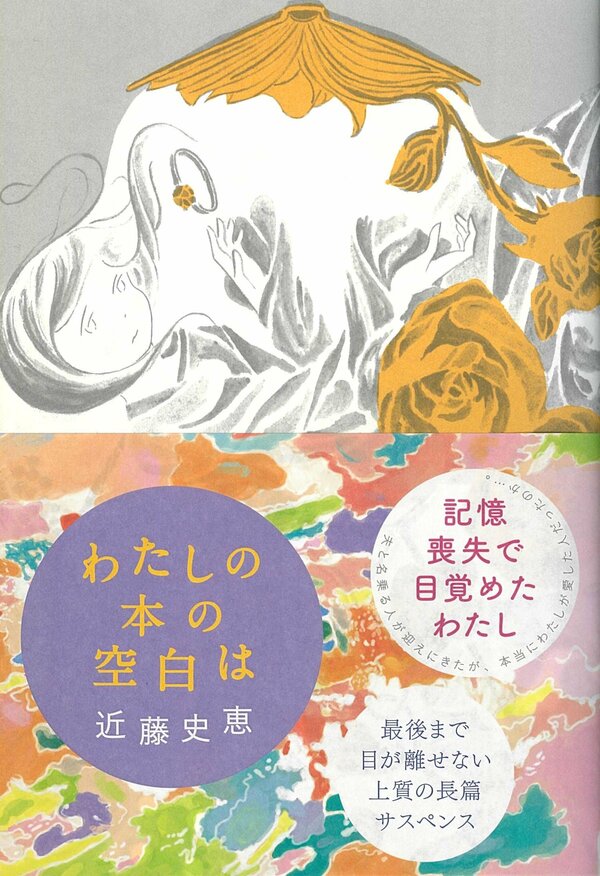記憶を失った「わたし」が
生きる“真実”を模索する
メディアで「記憶にない」という言葉を見聞きする度、不思議に思っていた。記憶とは言うなれば自分という媒体に刻みこまれた過去の情報。つまり人生は記憶で出来ているようなものなのに、あっさりなくしてしまえるものなのか、と。
かつて愛し、愛された記憶、叱られた記憶、祝福された記憶……たとえば昔住んだ家がなくなっても、壁の色や柱の小さな傷まで思い起こせる。そうした記憶を喪失するということは、人生の一部を失った状態でもあるだろう。
物語は病室から始まる。目覚めた「わたし」は、自分の名前も性別も年齢も覚えていなかった。なぜ自分がここにいるかもわからない。
やがて「三笠南」という自分の名前を知った「わたし」こと南は、妹・小雪や実家のことを思い出すが、夫・シンヤについての記憶は戻らないままだった。不安を抱えながらも退院するが、シンヤの姉・ユミから「なにもかも忘れて、実家に帰っちゃえば」と言われて、南は動揺する。
愛した覚えのない夫、認知症の姑、どこか冷たい義姉との同居。しかし記憶を取り戻すためにもこの辛い状況に南は慣れようとする。
それにしても記憶がないという感覚は恐ろしい。まさに本に空白の頁があるようなものだ。真実がわからないまま、白紙に夫が、もしくはその他の誰かが偽りの情報を書きこむ可能性だってある。そうなれば簡単に人生は改ざんされてしまうのだ。
一方、南はある日の夢に出てきた男性に惹かれている自分に気づく。
誰だかわからないが、その人が好きだった記憶が蘇ってくる。同時に自分を縛る夫への不信感を覚える南。
過去の記憶が戻らなくとも、現実の時間は進んでいき、やがて実際に夢の中の男性に出会い、心を確かめ合うが……。
冒頭で、人生は記憶で出来ているようなものと書いたが、記憶は自分の都合で無自覚に修正されもする。嫌な記憶は心の奥に押しやってしまいたいし、よい記憶はすぐ引き出せる場所に置いて、機会があれば人に語ったりもする。
こうして記憶を自分なりに形作ろうとするのは、ある意味人間の性(さが)でもあろう。人は嫌な記憶だけを抱えて生きていけない、と痛感する。
しかし幸せな記憶だけで生きていくことが良いとも思えない。失敗や後悔の記憶もまた人生の一部になり、そこから学ぶべきこともある。
物語のラストでは、記憶のずっと彼方へ連れ出された思いがした。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。