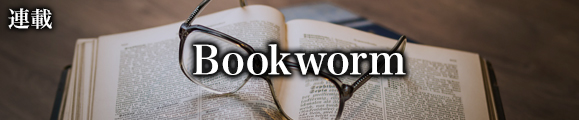亡き者たちと共に在るという実感
著者の筆が無類の輝きを放つ
死が終わりではなく、生と一続きになった世界を描いた物語だ。
今はここにいない者であっても、面影が心の乾板に複写されて、眼前にいるが如く鮮やかに蘇ることがある。そうした記憶の中にだけ姿を留める者たちを描かせたとき、小川洋子の筆は無類の輝きを放つのだ。
2012年の『ことり』(朝日文庫)以来7年ぶりとなる書き下ろし長篇『小箱』は、この世を去った者に、変わらぬ愛を注ぎ続ける人々を描いた小説である。いくつかの小川作品と同様に固有名詞が記されない、幻のような共同体が舞台だ。どこにあるかはわからないが、いずこかにはあれかし、と読者は思うだろう。
「私の住んでいる家は、昔、幼稚園だったので、何もかもが小振りにできている」と語り手の〈私〉が綴ることから『小箱』は始まる。あらゆるものが幼児サイズの家になぜ大人の彼女が、という読者の当然の疑問は、やがて明かされる事実によって解消される。幼稚園だった建物の講堂には4列の棚があり、そこにぎっしりとガラスの箱が詰められている。いずれも廃墟になった郷土史資料館から持ち出されたものである。
箱の中には死んだ子どもたちの持ち物が入っており、肉親は愛児の成長に合わせて中身を入れ替えるのである。〈私〉はその管理者なのだ。かつて資料館で過去の時間を閉じ込めていた箱に、今は子どもの未来が保存されている。不在の子らは箱の中で年をとり、成人し、結婚までする。
主人公を頻繁に訪問する男性、通称〈バリトンさん〉は資料館の元学芸員だった。読んでいるうちに、この世界には「元」が多いことに気づかされる。かつては多くの子どもたちを診ていた元歯科医師は、今は小さな小さな竪琴を作っている。元美容師が遺髪でその竪琴に弦を張る。子どもの親たちは風のある晩にそれを耳たぶにつけ、自分にだけ届く調べが聴こえてくるのを待つのだ。
ページをめくっていくうちに読者は、この物語に欠けている要素があることに気づくだろう。世界の時は停まっており、だんだんと消え始めているようにさえ見える。夜空で少しずつ身を細らせていく月の如く。
もうすぐなくなってしまうかもしれない場所で、しかし決して絶望することなく人々は日々を送っている。亡き者たちと共に在るという生の実感があるからだ。おそらく死者の声は小さくて、本当に求める者の耳にしか届かないのだろう。かそけき声が聴こえてくるまで、幾度でも読みたい気持ちにさせてくれる。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。