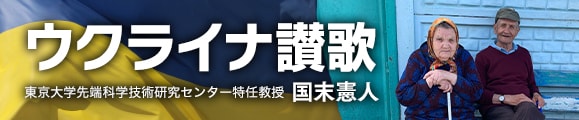前回筆者がウクライナに滞在した2022年12月~23年1月の冬は、ロシア軍による電力施設攻撃が集中して停電が多く、首都キーウは暗闇に包まれていた。ロシア軍の侵攻当初に比べると人が戻っていたものの、一部の商店や飲食店は閉まったままで、市民が生活を謳歌する状況にはなかった。
今回、街の賑わいぶりは明らかに異なるレベルである。店は軒並み開き、中心街ではショッピングを楽しむ市民が目立つ。ミサイルやドローンによる攻撃を知らせる警報は毎日のように鳴り響くが、反応する人はほとんどいない。迎撃態勢が整い、多くの攻撃は阻止されているからだろう。破片の落下でけが人がしばしば出るとはいえ、それほどの脅威とは受け止められず、日常生活は中断されることなく続く。欧州の他の街との違いは、午前0時~5時の夜間外出禁止に備え、夜の街が比較的早くしまう点ぐらいだろうか。
ただ、街の「正常化」は、普通の社会に存在する様々な負の側面も同時に復活させた。人々を結びつけていた国家防衛の一体感も薄れ、雑音や不協和音も漏れるようになっている。
ウクライナ社会の現状と人々の意識を探ろうと、キーウ市内に有識者を訪ねた。

さもなくば死か
最初に会ったのは、ウクライナ公共放送の会長ミコラ・チェルノティツィキー(40)である。若くしてその手腕を買われ、日本だとNHKにあたる巨大メディアの舵取りを任された。政界ともつながりが強い大物だが、気さくでユーモアにあふれ、笑顔を絶やさない。ワサビが大好物で、昨年の来日時に新宿で一緒に飲んだ際は、刺身のワサビを何度もお代わりした。

ミコラは、ウクライナ社会に起きた最近の変化を列挙した。
①:ロシア語が聞こえてこなくなった。ロシア語を母語とする人でさえ、ロシア語を話そうとしない。これまでは街中にロシア語の歌が流れていたが、それも全くなくなった。
②:社会に様々な制限が課されるようになった。ウクライナの男性は外国への渡航を禁止されているし、夜間は外出禁止令が敷かれている。
「でも、反面それはいい習慣を根付かせたのです。今まで私たちは、午前2時、3時まで平気で飲んでいました。夜間外出禁止令によって、みんな早々と家に帰るようになったのですから(笑)」
③:大統領ヴォロディミル・ゼレンスキーへの支持率は依然高いが、今年2月に軍総司令官ヴァレリー・ザルジニーを解任した際には少し陰りが見えた。その原因はゼレンスキーの説明不足にあった。
④:世間に不安は広がっている。
「日常生活面での大きな変化は、将来が計画できなくなったことです。戦争前は『夏になったらこれをしよう』『あそこに行こう』などと予定を考えていました。今は、明日明後日ぐらいの予定しか立たない。将来何が起きるのか、みんなわからないのです」
その結果、心理カウンセラーに通う人が増え、今やこの職業は大人気だという。
「反転攻勢の失敗は、大きな失望に結びつきました。私たちは、今まで、この戦争について『絶対勝てる』と言い過ぎた。期待を抱きすぎたのです」
ミコラはこう説明する。
では、その失望が、停戦や和平を求める声につながっているだろうか。ウクライナでは以前、そのような声は皆無に近かった。2022年11月に「ミュンヘン安全保障会議」(MSC)がウクライナで実施した世論調査で、ロシア軍の占領が続く状態での停戦を求めた人は、わずか1%だった。停戦の条件として、93%が「クリミア半島を含むウクライナ全土からのロシア軍の撤退」を挙げた。その世論に変化はあるか。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。