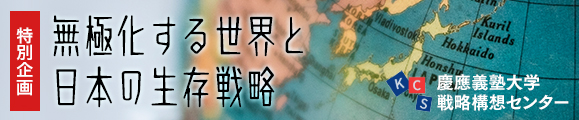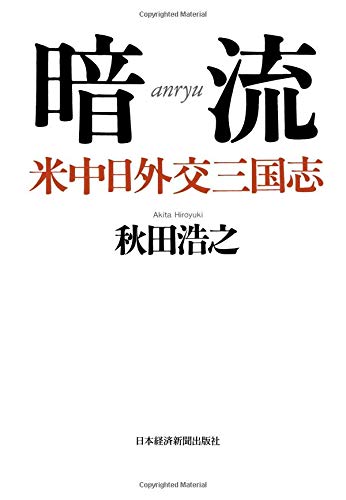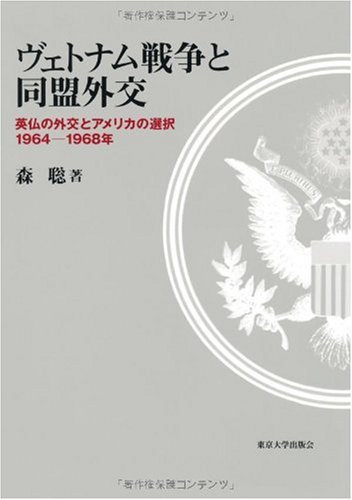【特別公開シンポジウム】アメリカ新政権と無極化する世界のゆくえ(3)
※2024年11月11日開催の講演内容をもとに、編集・再構成を加えてあります
米中対立をどう見るか
森 最後に三つ目に米中対立についてですが、台湾を巡ってアメリカと中国が緊張を高めるという状況はおそらくこのまま続きます。ただ、台湾への戦略的曖昧性に関する宣言政策のレベルでは、トランプ大統領とホワイトハウスの役割分担が、バイデン政権の時と逆になるのではないか。どういうことかといいますと、バイデン政権では大統領が「もし中国が台湾を攻めたらアメリカは台湾を防衛する」と“失言”し、ホワイトハウスが「既存の政策に変更はない」とフォローアップする、というのが戦略的曖昧性を維持する形として既定路線になっていました。しかし次のトランプ政権では、むしろ外交・安保チームが台湾防衛に積極的になる可能性があります。台湾に対して防衛努力の強化を求め、武器売却も積極的に行って対中抑止のための軍備強化もやるし、部隊の展開もやるしということで、中国に対するバランシング、対抗、封じ込めが、より鮮明になる。他方で、トランプさんは「中国がもし台湾に攻め込んだら追加関税200%だ」といいつつも、軍事的にどう対応するのかははっきりさせない。「どう対応するか明らかにしたくない」とトランプさんは言っています。このように、曖昧さのロジックはバイデン政権と全く違うものになりますが、役割としては大統領の方が曖昧にするという宣言政策になるのではないかと思います。
そして、トランプ大統領やヴァンス副大統領のような抑制主義者が追加関税など経済面での厳しい駆け引きを行い、外交・安保チームは対中抑止戦略を進めるということで、次のトランプ政権は少なくとも当初は、全体的に強硬な対中スタンスをとるところから始める見ていいでしょう。ただそれは平時の話で、正念場になるのは危機が起こった時ですね。危機に臨んだトランプさんがどのような判断を下すのかは本当にわからない。台湾を守るために中国との全面戦争を覚悟するかというと、正直なところ疑問です。
ここに至って初めて、抑制主義者と優先主義者の主張が乖離するわけです。トランプさんは、おそらく台湾周辺に部隊を急派するところまでは優先主義者と意見が一致する。けれども、優先主義者なら開戦を辞さない構えをとりますが、トランプさんは習近平に電話をかけて、「第3次世界大戦の危機を脱するためにディールをしなければならない」と伝えるでしょう。そのディールの中身が何になるかは分かりませんが、例えば中国側は台湾の主権を取り、人民解放軍の段階的駐留など統一のためのスケジュールをアメリカ側に認めさせる。アメリカは半導体の購入など平常のビジネスは維持でき、その他の見返りを中国から得るというようなことが想定できます。もし取引に失敗すれば、意図せずして武力衝突に至るか、アメリカが屈辱的な立場に追い込まれることになってしまいます。
こんなシナリオが現実化しないことを願うばかりですし、荒唐無稽に感じられるかもしれませんが、それすらも想定すべき局面に来ているのは事実です。中国側が危機を4年以内に引き起こすというつもりはありません。ただ、中国側の視点に立てば、日米の抑止力強化が進めば進むほど自国の軍事オプションの有効性が薄れるわけですから、習近平さんがディール志向のトランプさんが開ける「機会の窓」を逃さず活かそうとすることは考えられます。それは危機や戦争ではなく、外交かもしれません。こうしたことが安全保障上の新たなリスクとして浮上してくる可能性もあると考えています。
秋田 ありがとうございます。二点申し上げたいと思います。一点目は、今の森先生からいただいたコメントを踏まえ、日本はどうすればいいのかということです。二点目は、細谷先生からお話のあった世界戦争の危険も含め、米中関係についてです。
まず一点目、準備すべきはプランBなのか、あるいはプランAダッシュダッシュなのかという問題ですが、この二つでやるべきことは大きく重なると思うんです。違いとしてはおそらく、核抑止力を自分で持つか(プランB)、それともアメリカの核の傘に頼るか(プランAダッシュダッシュ)。アメリカに頼らないのなら、核の傘がないのをどうするか考えなければいけなくなります。ただ、防衛費の増大など日本がやらなければいけないことの項目はほとんど同じですから、私の意見としては、議論はプランBになってもいいぐらいのつもりで安全保障に取り組んだ方がよいだろうというところです。
その上で、日本はどう行動すればいいのか、です。これについては三つのパターンがあると思います。一つはアメリカが関与してくれるという前提をいちど保留し、自律性を高めること。二つ目は、対米関係をなんとかケアして、現状の前提を維持すること。三つ目は、先ほど森先生がおっしゃったアメリカへのエンゲージです。少し具体的にお話しします。
私は先月、ロシアと隣接したラトビアの首都、リガで開かれた国際会議に参加しました。アメリカや欧州の高官・識者が集まって安全保障について話し合う場だったのですけれども、ここでもやはりトランプさん再選ならばどうなるかが大きな論点になっていました。印象的だったのは、「アメリカが欧州の安全保障に関与し続けるというフィクションを信じ込むのは、もうやめようじゃないか」という声があったことです。特にフランスなどはこうした意見が強かった。
これは「アメリカを信じない」ということではないんです。疲れて内部を立て直さなきゃいけないアメリカが、欧州に関与し続けてくれると単純に期待し続けるのはリスクになる、ということですね。日本もこういう前提で行動するのが、いま申し上げた一つ目、「前提保留かつ自律」のパターンです。
二つ目の「前提維持・対米ケア」はどういうことかと言いますと、「一生懸命、トランプさんに抱きつけば何とかなる」みたいな意識に基づく行動ですね。石破さんにトランプさんとゴルフをやってもらって、安倍さんみたいにハンバーガーを食べてもらって、何とか個人的な関係を深めることで乗り切ろうという労線ですでも、これはもう持続しませんでしょう。
三つ目の対米エンゲージは、一つ目の「前提留保かつ自律」に近い行動パターンです。ただ、まさに森先生がご指摘のように、日本が「自立します」と言ったら日米同盟を冷やす危険がある。下手をすると「この家を出るなら赤の他人だ」ということになりかねない。ここは非常に気を付けなければなりません。アメリカと同じ家、傘の下にいるのだけれど、その中で自分のやれることを増やすという、英語で言えば「autonomous」の方向性をうまく打ち出すことがまず大事です。そして、これを確保しながら、トランプさんに「アメリカを再び偉大にするというあなたの挑戦には全面的に賛成するし、協力を惜しまない。日本もアメリカと一緒に偉大になる」というアプローチをするのが一番よいのだろうと思います。
それから、細谷先生のご発言にもあった米中対立と世界戦争の危険についてです。米中対立は三段階を経て、かなり危ないレベルにきていると考えます。
第一段階の米中対立は、オバマ大統領の二期目からコロナが発生するまでがこれにあたります。当時はまだ冷戦の一歩手前で、南シナ海での領有権問題やサイバー攻撃に関する対立でした。これは、「こっちの縄張りに勝手に家を建てるな」「俺の電子マネーを盗るな」というような、いわばモノや利益の奪い合いのレベルだったと思うんです。これは盗ったものは元の持ち主に返す、建ててしまった家は取り壊すで、対立を修復することも可能でしょう。
ところが第二段階のコロナ禍、これは第一次トランプ政権の途中からになりますが、ここでは100万人以上のアメリカ人が死んだわけです。第一次・第二次の世界大戦とベトナム戦争の合計戦死者数を超える人間が命を落とした。すごい数です。この時、中国共産党というのは情報を公開しない、原因の調査もさせない、非常に危険な体制だという認識がトランプ氏本人も含めてアメリカの政権に定着した。これはもう縄張りやお金の問題ではなく、人間で言えば「性格が違う」と言いますか、中国の姿勢が受け入れられない、危険だというレベルになるわけです。私はここが米中冷戦の始まりだと書きました。
第三段階がロシアによるウクライナ侵略から現在です。中国はロシアを批判せず、むしろ軍民両用物資を輸出するなど水面下で支援した。アメリカは、ロシアの不器量産に使われている電子精密部品と工作機械の7~8割は中国から来ていると見ています。こうなりますと、人間で言うならもう「人生観、世界観が違う」と言いますか、米中の考える世界のあるべき姿そのものが違っている。性格が違っても人生観を共有できる人となら、意外にうまくやれることもあるでしょう。でも人生観が違ってしまうと、かなり厳しい。
こういう間柄では、喧嘩になる時の沸点が下がります。台湾の問題でも、南シナ海問題を巡っても、大きな衝突に繋がる可能性は高まっている。いまの米中はそういうレベルに来ていると思います。トランプ政権は国内のことで精一杯という面もありますが、一方で、「コロナのせいで再選できなかった」とか「偉大になるべきはアメリカなのに、中国が偉大になろうとしている」といった部分で、激しく怒ってもいるわけです。ですから、たとえば台湾をめぐってその怒りが噴出するのか、それでも中国とは戦わずにディールしようとなるのかは、もうその瞬間になってみないとわからない。水と油の発想が、トランプさんの中でぶつかるのだと思うんです。
細谷 鶴岡さんにお話しいただく前に森さん、追加のコメントはありますか?
森 度々すみません、米中関係のパターンと今後の展望についての視座を加えさせてください。それは民主党政権と共和党政権では中国と競争するうえでのスタイルが違うということです。
民主党政権は基本的にはマラソンのイメージで、直接的なコンタクトをして争うことは避け、安定した状況で国力増進の競争をする。自分たちの政治経済体制の方が中国よりも上回っているんだぞ、というイメージで競争しているところがあります。これに対して共和党政権、トランプ政権の方は、レスリングのように組み合って圧力をかけ、中国を譲歩させて取りたいものを引き出す競争のイメージです。これは安全保障よりも経済分野で顕著ですね。
おそらく政権交代が起きるたびに、レスリング型とマラソン型の競争が交互にやってきて緊張と緩和が繰り返される。外形的に見るとジグザグに展開していく可能性を念頭に置くべきではないかと思います。
細谷 ありがとうございます。続けて鶴岡さんからも、何か補足があればお願いします。
鶴岡 まず米中の話ですと、米中が世界を規定していくことに一番危機感を持っているのは、やはりヨーロッパだということです。自分たちが取り残されてしまうという懸念ですね。
これについては、だからこそアメリカに一層近づいて、アメリカ側に加勢するような形で存在感を示すという選択肢が一つあるわけです。そして実際、過去10年ほどのヨーロッパの対中認識は、全体としてはやはりアメリカに近づいていったのだと思います。しかもバイデン政権期というのは、米欧関係という視点で見ると、これほど対立がなかった4年間は珍しいと言えそうです。とにかくトランプ政権が終わって良かった、バイデンがやることはトランプよりマシという感覚がヨーロッパに強くあった。それと同時に、バイデン政権はヨーロッパに対して、表に加えて裏でも徹底的に根回しを行っていたはずです。この根回しの真剣度や深さも、おそらく今までのアメリカの政権とは違っていたでしょう。
ただ、アメリカに近づくことで世界が米中によって規定されるのを乗り切るという発想は、ヨーロッパの中ではコンセンサスではないんですね。「アメリカと一緒になって中国と戦うのはおかしい」という巻き込まれ論的な懸念は、やはり常にヨーロッパにある。ここで、バイデン政権のアメリカだったら「まあ、とりあえず信用してついていくか」という人たちが多かったかもしれないのですが、トランプ政権になると「あのトランプについていって中国と事を構えるのか?」ということになる。やはりアメリカと行動を共にすることへの支持率は、トランプ政権下では下がらざるを得ないのだと思います。しかも、米中関係をエスカレーションさせているのはアメリカだという認識がもしヨーロッパで広まれば、それは対中政策における米欧接近を妨げる更に大きな要因となるでしょう。
ここでもう一点考えるべきは、ヨーロッパの中にトランプ政権と繋がっている、あるいはトランプ的な考え方に親和性を持っている勢力が、かなり増えてきているということです。右派や極右、あるいはホロコースト否定論者のような極右と区別する意味で「ハードライト(強硬右派)」と呼ばれるイタリアのメローニ政権やポーランドのドゥダ大統領のような――ハンガリーのオルバン政権をどう見るかはなかなか難しいものもありますが――トランプ政権に親和性がある勢力が拡大してきている現実もあるんですね。旧来型エスタブリッシュメントの中道右派・中道左派にある「トランプは絶対に嫌だ」という拒否反応と、強硬右派らの「むしろトランプ政権の方がいい」という反応が今は渾然一体となっていて、全体の方向としてどちらに転ぶかはまだわからない。
それから「プランAダッシュダッシュ」と「プランB」の話については、まさに秋田さんご指摘のように、結局やらなければならないことはほとんど一緒なのだと思います。ただ、これを日本がどう捉えるか、どのようにアメリカにプレゼンするかには、やはり大きな違いもあるでしょう。それは、バードンシェアリングで役割を果たしているとアピールしてアメリカの関与を永続化させようという、手段としての自律性(autonomy)なのか、autonomy自体が目的になるのかという違いです。プランBというのはおそらく、autonomyを目的にしないと最後は成立しないと思うんですね。それに対してプランAは、ダッシュをいくつ付けても、結局はアメリカを引き留めるための手段としてautonomyやバードンシェアリングを使うわけです。
これはトランプ政権一期目のヨーロッパもそうだったわけですけれども、「今度こそ本当に自律しないといけないかもしれない」とみんなが身構えるわけですが、結局は何となく過ぎていく。アメリカの方も、ヨーロッパあるいは日本が本当に自律すれば、これはある意味ではアメリカが「普通の国」になるということで、少なくとも第一次トランプ政権にそれをよしとするコンセンサスはなかったのだと思います。今後、本当に「アメリカは普通の国でいいのだ」ということになっていくのかは、まさにヨーロッパも固唾をのんで見守っているところです。
今までのような、落としどころが前もってわかっているバードンシェアリングをめぐるゲームが本質的に変わるのか、変わらないのか。「負担しろ」とアメリカが言って、同盟国が負担すれば「よし。じゃあもうちょっと同盟を続ける」というアメリカと同盟国の関係における狂言のような部分がどうなっていくかというあたり、しっかり見ていかないといけない点だと思います。
細谷 ヨーロッパの視点も含めて、大変貴重な問題提起をしていただきました。
[質疑応答略]
お陰様で大変有意義なディスカッションができました。改めて登壇者の先生方に感謝を申し上げてこのシンポジウムを終えたいと思います。皆様どうもありがとうございました。