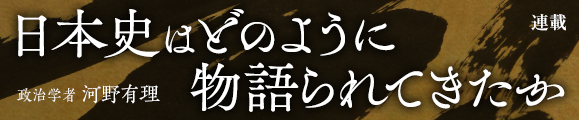本連載では、さまざまな「日本史」を並べて比べ見るということをしてみたい。ここでの「日本史」には、「日本という国や社会についてのある程度のまとまった長さを扱う歴史記述」といった程度の曖昧な定義を与えておきたい。想定している典型的な例は、個人の著作、つまり一人の手で書かれた日本の「通史」である。独力でというのが大事なところなので、たとえ書名として「日本通史」と銘打っていても複数人が時代別に分担して執筆したものは含めない。したがって、(その読者数はきわめて多いはずだが)いわゆる山川出版社『日本史』などの教科書類もこれに含めない。教科書は通常、複数人で執筆され、しかも検定を経て刊行されるからである。本連載は、個人が一人で書いた「通史」としての日本史を、主として取り上げる予定である。
もっとも、「通史」といってもその定義もまたなかなか難しい。そもそもどの時代から話を始めれば「通史」になるのかは必ずしも自明ではない。それはどのような時間的・空間的まとまりを「日本」とみなすかという著者の「史眼」や「史観」と、密接不可分に結びついているからである。したがって、ここでいう「通史」というのも、歴史的事象を漏れなく満遍なく、バランスよく扱っている歴史叙述であるということを必ずしも含意しないことは強調しておきたい。むしろ反対に、本来無限に存在する歴史的事象のうちで何をどのように取捨選択するか、その結果としてある「まとまり」をいかにして造形するか、そうしたことを意識している歴史叙述のことをここでは「通史」的な仕事として意識しているというわけである。「まとまり」の長さではなく、それを切り出す際の「史眼」や「史観」に注目するというのが肝心なところである。
本連載では、アカデミックな歴史学の訓練を受けた狭義の歴史学者だけでなく、作家やジャーナリストの書いた「日本史」も扱う予定である(むしろそちらの場合の方が多いかもしれない)。それはアカデミズムに属する歴史学者は専門性を重視するあまり「史眼」「史観」の露出に禁欲的である場合が少なくないからである(アカデミックな通史が通常は複数人で分担執筆されるのもそのためである)。また、上記のような趣旨から、純然たる創作物、たとえばいわゆる歴史小説も扱う予定である。一見すると「通史」という字面からは離れてしまうように見えるかもしれないが、お許し頂ければ幸いである。
歴史を「まとまり」として記述する
では、「史眼」「史観」に沿って切り出される「まとまり」としての日本史。それを並べて見ていく際に、どのような点を意識するのか、あるいはどのような点をあえて意識しないのか。
第一に、ファクトチェックは重視しない。重視しないというと語弊があるかもしれない。「史実」と合致しているか否か。合致していれば100点満点、していなければ0点という態度では臨まないということである。本連載で扱っていく過去の日本史叙述については、当然、研究の進展に伴い、現在では誤りとされている記述が多く含まれている。こうした記述については、当然、気づいた限りで指摘していくことにしたい。だが、「史実とは違いますね」ということで話を終わらせるより、むしろその「誤り」によってどのような「おはなし」が可能になっているかということに着目したい。歴史叙述が客観的事実と適合しているか否かよりも、その歴史叙述が持っている「おはなし」(ナラティブ)性の方に多く照明を当てたいということである。
第二に、そうした「おはなし」(ナラティブ)について、規範的評価はさしあたり行わない。つまり、その善悪を問わないということである。これはそのそれぞれの「おはなし」が含意しているある種の規範的主張、「こういう日本はいい(悪い)」を無視するという趣旨ではない。むしろ、それはその「おはなし」の「読みどころ」であろう。ここで善悪を問わない、とはそういった「おはなし」についての道徳的善悪を評価の基準にしないということである。極端に単純化した例をあえてあげるとすれば、「これは日本を悪く書いているから良い」とか「これは日本を良く書いてあるから悪い」といった評価の仕方をしないということである。
それはもちろん、筆者がすべての価値判断から中立な立場を維持しているということを意味しない。本連載は、「日本」というまとまりの「歴史」を扱うという点で明らかに選択的な価値判断を行っている。
歴史は、日本であれ韓国であれ米国であれ、政治共同体の単位に応じて書かれる必要は必ずしもない。個人の歴史があり、地域の歴史があり、世界(グローバル)の歴史があり、人類という種の歴史があろう。そうした様々に書かれうる可能性のある歴史のなかで本連載では、わざわざ「日本」という政治共同体に応じて書かれた歴史叙述に関心を持っているのである。その意味に限っては、たとえば本書は百田尚樹『日本国紀』ともその関心の範囲を共有していると言える。ついでに言えば、詳しくは次回で扱うように、近年では自国の歴史を「まとまり」として記述することに関心を寄せるのは、保守や右翼的な政治思想に特徴的な性格となりつつある。これまた歴史的現象であり、過去において事態は必ずしもそうではなかったにもかかわらず徐々にそうなってきたのである。なぜそうなったのかは本連載の関心の一つである。
同じ問題を「歴史」という視点の方から考え直してみよう。日本であれどこであれ、ある政治共同体についてその行く末を考えるにあたり、歴史を参照する必要はこれまた必ずしもあるわけではない。あるべき国家像や社会像の模索はおそらく歴史抜きに可能である。歴史抜きで政治共同体のあるべき姿を考える方法の一つとして、たとえば戦後日本の政治思想史研究で一世を風靡した社会契約論がある。いくつかの超時間的な原理原則から出発して演繹的にあるべき社会の姿を構成する――政治思想史的にいえばたとえばJ・ロールズの正義論はその最新のバージョンであるといえよう――という方法である。もっとお手軽な方法としては、「準拠国」や「模範国」を定め、それをベンチマークとして現在の社会の状態を批判的に眺めるというやり方がある。この場合、「準拠国」「模範国」の選択は、往々、いくつかの原理原則に基づいた理想を多く含有しているかどうかがその理由となるので、この方法はいわば社会契約論的な方法のいくぶん粗雑な系(コロラリー)ということになるだろう。
また、社会契約論はもちろん、「準拠国」「模範国」の観念が無いからといって人々が歴史の価値を見直すわけではないことは、近年の日本社会を見れば明らかであろう。SNSにおける「炎上」に顕著なように、過去の問題がその脈絡や文脈が公共的に蓄積されることなく、定期的に再炎上を繰り返す。いつまでも話はループし、前には進まない。かつて丸山眞男は議論が座標軸上に沿って「伝統」として蓄積されず絶えず一から話が蒸し返され続ける日本社会のあり方を嘆き、その克服を目指していた(『日本の思想』)。だが、SNSの定着とともに、むしろそうした恒常的「再炎上」の方が、日本どころか世界の常態になりつつあるのかもしれない。そこで、伝統的に文化人類学が扱ってきた無文字社会でしばしばみられるような、「歴史の無い社会」をやり過ごす知恵を洗練させるべきではないかと提案する識者も現れた(與那覇潤『歴史なき時代に――私たちが失ったもの 取り戻すもの』)。
反対に、社会の行く末を考え行動するに際し、歴史に強固なこだわりを見せたのはたとえばマルクス主義であった。マルクス主義はあるべき「世界史」を持ち、その「発展段階」のどこに位置するかがすなわち行動の羅針盤となった。歴史こそが「現在、どうすべきか」を照らす光であったのである。「日本」というまとまりの歴史を扱い、その「おはなし」(ナラティブ)に含まれる政治共同体にとっての規範的含意を対象とする本連載は、この意味では(そしてやはりこの意味に限り)、マルクス主義ともその姿勢を同じくすると言える。マルクス主義の言う歴史の「法則」には全く信をおかないとはいえ、歴史が私たちの社会の行く末を考える際に全く不要であるとまで考えることはできない。それが本連載の立場である。
「面白いおはなし」としての歴史物語
以上、要するに歴史の書き方についても、「日本」という政治共同体の行く末の考え方についても、著者はある特定の(決して当たり前ではない)立場にコミットしている。そんな本連載が、それぞれの「日本史」についてでは、どの点を評価するのか。それは巧拙であり、あえていえば「面白い」か「面白くない」かである――
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。